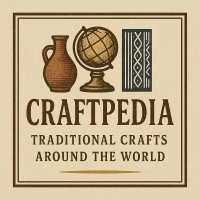Shiro Satsuma
From Global Knowledge Compendium of Traditional Crafts and Artisanal Techniques

白薩摩(しろさつま)は、薩摩藩(現在の鹿児島県)発祥の、高度に洗練された日本の陶器の一種です。象牙色の釉薬、精巧な多色釉、そして独特の細かいひび割れ模様(貫入)で知られています。白薩摩は日本の陶磁器の中でも最も高く評価されているものの一つであり、特に明治時代(1868~1912年)には西洋で高い評価を得ました。
歴史
白薩摩の起源は17世紀初頭に遡ります。朝鮮出兵(1592~1598年)の後、島津氏によって朝鮮の陶工が南九州に招かれました。彼らは薩摩藩に窯を築き、様々な陶磁器を生産しました。
時が経つにつれ、薩摩焼には主に3つの種類が生まれました。
- 黒薩摩(黒薩摩):鉄分を多く含む粘土から作られた、素朴な暗い色調の炻器。厚く丈夫で、主に日用品や地元での使用に使用されました。
- 白薩摩(白薩摩):精製された白土から作られ、細かいひび割れ(貫入)が特徴的な半透明の象牙色の釉薬で覆われています。これらの作品は、支配階級の武家や貴族のために作られ、優雅で控えめなデザインのものが多かったです。
- 輸出薩摩(輸出薩摩):白薩摩の発展形で、江戸時代後期から明治時代にかけて、特に海外市場向けに作られました。これらの作品は非常に装飾的で、金彩や色絵の具が厚く施され、西洋人の嗜好に合うように異国情緒あふれる物語風の情景が描かれていました。
特徴
Shiro Satsuma は以下の点で有名です:
- 象牙色の釉:温かみのあるクリームのような肌触りで、ほのかな透明感があります。
- 貫入釉:意図的に織り込まれた微細なひび割れ模様が、この器の特徴です。
- 多色上絵付け:一般的に金、赤、緑、青の釉薬が用いられます。
- モチーフ:
- 貴婦人や廷臣
- 宗教的な人物(観音様など)
- 自然(花、鳥、風景)
- 神話や歴史を題材にした情景(特に輸出薩摩焼)
テクニック
製造プロセスには以下が含まれます。
- 精製した粘土から器を成形する。
- 素焼きして硬化させる。
- 象牙色の釉薬をかけ、再度焼成する。
- 上絵付けと金彩で装飾を施す。
- 低温で複数回焼成し、層ごとに装飾を融合させる。
各作品、特に非常に精巧な輸出用薩摩の作品の完成には数週間かかることがあります。
輸出時代と国際的な名声
明治時代、シロサツマは西洋人の日本美術への関心を満たすために変革を遂げました。これにより「輸出薩摩」と呼ばれるサブジャンルが生まれ、以下の万国博覧会などで展示されました。
- 1867年 パリ万国博覧会
- 1873年 ウィーン万国博覧会
- 1876年 フィラデルフィア万国博覧会
これにより、薩摩焼は世界的な人気を獲得しました。輸出時代に活躍した著名な作家や工房には、以下のようなものがあります。
- Yabu Meizan (矢部米山)
- Kinkōzan (錦光山)
- Chin Jukan kilns (沈壽官)
現代の文脈
伝統的な白薩摩の生産は衰退しましたが、日本の陶磁器の卓越性を象徴する存在であり続けています。アンティークの白薩摩や輸出薩摩は、現在、コレクターや美術館で非常に人気があります。鹿児島では、薩摩焼の伝統を守り、新たな解釈で表現する陶工が数多くいます。
==薩摩焼の種類==
| 種類 | 説明 | 用途 |
|---|---|---|
| 黒薩摩 | 地元の土から作られた、暗く素朴な炻器 | 領内での日常的な実用 |
| 白薩摩 | ひび割れや繊細な装飾が施された、優美な象牙釉の陶器 | 大名や貴族が使用。儀式や展示に |
| 輸出用薩摩 | 西洋のコレクター向けに、金を多用し、鮮やかな絵柄をあしらった、豪華な装飾の陶器 | 輸出市場(ヨーロッパおよび北米)向けの装飾美術 |
参照
Audio
| Language | Audio |
|---|---|
| English |