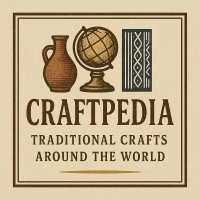柿右衛門焼
柿右衛門(かきえもん)は、日本の磁器の様式の一つで、釉薬をかけた「ホーロー」と呼ばれる装飾が施されています。この様式は酒井田家に起源を持ち、17世紀半ばの江戸時代から肥前国(現在の佐賀県)有田町の窯で生産されていました。その装飾のクオリティは高く評価され、ロココ時代にはヨーロッパの主要な磁器メーカーによって広く模倣されました。
歴史
初代酒井田柿右衛門は、双子の柿(かき)の図案を完成させ、柔らかな赤、黄、青、そしてターコイズグリーンを基調とした独特の色彩を創作したことから、主君から「柿右衛門」の名を賜りました。この色彩は、現在では柿右衛門様式の象徴となっています。初代酒井田柿右衛門は、日本で初めて磁器に色絵を施した陶芸家の一人とされており、この技法は1643年に長崎の中国人職人から学んだと伝えられています。
明朝の滅亡により伝統的な中国磁器のヨーロッパへの輸出が途絶えたことで、この様式は隆盛を極めました。柿右衛門磁器は1650年代からオランダ東インド会社を通じて日本からヨーロッパへ輸出されました。18世紀には、ドイツのマイセン、フランスのシャンティイ、イギリスのチェルシーなど、ヨーロッパの新興磁器工房が次々とこの様式を模倣しました。1760年頃までに、柿右衛門様式はヨーロッパではほとんど流行らなくなりました。
特徴
柿右衛門焼は、より広範な有田焼のサブタイプであり、高品質で繊細、そして左右非対称な意匠で知られています。これらの意匠は、日本では「濁手(にごしで)」と呼ばれる、乳白色の磁器の繊細な地色を強調するために、まばらに施されています。磁器の素地は、八角形、六角形、または正方形を特徴とするものが多くありました。
柿右衛門の色彩パレットの特徴的な色彩は、赤鉄色、水色、青緑、黄色で、時には少量の金箔が用いられることもあります。一般的な装飾テーマには以下が含まれます。
- 「鶉と粟」の図案:小枝の葉と小さな鶉が描かれています。
- 「冬の三友」:松、梅、竹が描かれています。
- 「井戸端会議」:中国の有名な民話を題材にしています。
- 鳥とムササビ
- 花、特に菊が描かれています。
Kakiemon pieces can be found in a number of museum collections around the world. The style is still produced by the Sakaida family and other artisans today.
Audio
| Language | Audio |
|---|---|
| English |